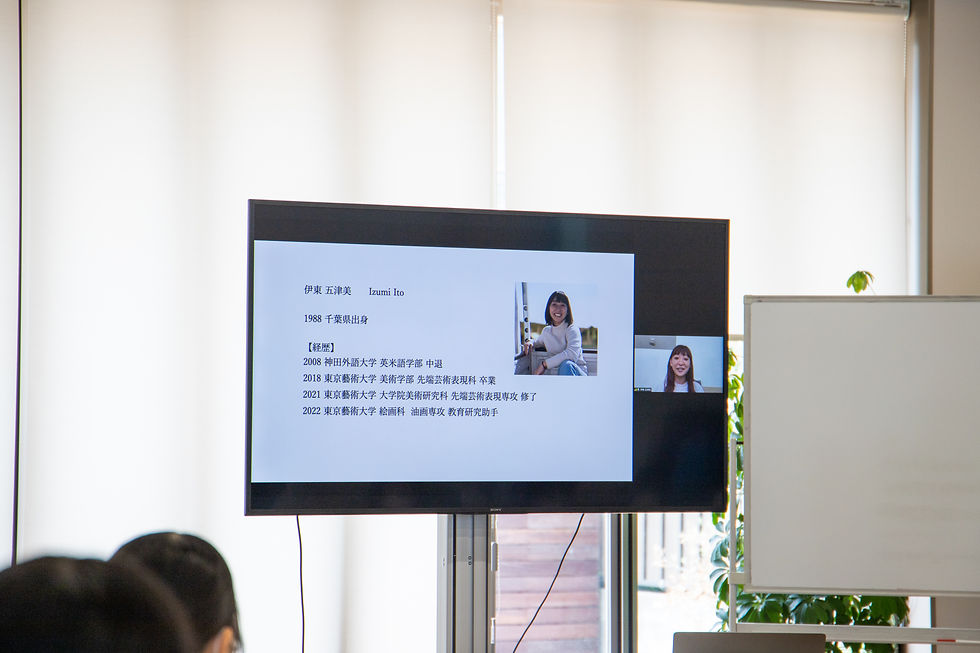- 香川大学柴田研
- 2022年8月23日
更新日:2023年5月17日
2022年8月22日 午後1
午後の部の最初は、香川県の海ゴミリーダーこと森田桂治さんに海ゴミについての基礎知識についての講義をいただきました。海ゴミが環境に与える影響や問題を、海洋動物になりきった実演や実際に海ゴミの分別を通して、より身近に問題として感じることができたように思います。「海ゴミを減らすために私たちは何ができるのか?」という漠然とした問いに対して、海に関係するそれぞれの立場からさまざまな答えを模索していく必要がることに気付かされました。



2022年8月22日 午後2
午後の部2つ目は、東京藝術大学教授の橋本和幸先生に、ドローイング演習です。「海の記憶」をテーマに、高校生とアーティストが、海にまつわる記憶を自由に描きました。描いた絵をみんなの前で発表し、それぞれの海に対する想いの違いやどこか懐かしさを感じる共通点などを共有しました。


2022年8月22日 午後3
午後の部最後は、香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 副機構長ならびに危機管理先端教育研究センター長の長谷川修一先生に、香川の地質と文化の関係を詳しく講義していただきました。ジオ(地質)の視点から、その上に成り立つ生活や文化を紐解く講義では、香川のうどんやアートがなぜこの土地で発展していくかを大地の視点から解説いただきました。普段住んでいる香川県の新しい見方を発見する機会になりました。


これで、1日目のプログラムは終了しました。自分が瀬戸内海の里と海に対してどのくらいの理解ができているのか。瀬戸内海と自分の距離がはっきりとわかるような日だったと思います。2日目以降では、その距離をもっと縮めていきたいなという思いをこめて、1日目の記事は締めくくらせていただきます。